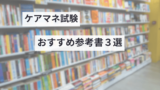現在、介護福祉士として現場で介護のお仕事をされている方の中には、今後はケアマネージャー(介護支援専門員)になって活動したいと考えている方もいるだろう。
筆者は社会福祉士として地域包括支援センターに勤務していたため、その業務を通じてたくさんのケアマネージャーに出会ってきた。もちろん介護福祉士出身のケアマネージャーも多く居た。ケアマネになるには必ずしも介護福祉士である必要はないのだが、ケアマネ試験の受験者の中で最も多くを占めるのが介護福祉士である。
さて筆者が出会ってきたケアマネージャーの中には、ケアマネとしてバリバリ活躍される方がいる一方で、ケアマネに転身したものの自分には合わないと判断し、早々に介護職に戻る方も少なくはなかった。
今日は『介護福祉士からケアマネになること』のメリットと、ケアマネが合わなかったという人たちの言葉も紹介していきたい。
※筆者は社会福祉士であり、介護福祉士ではない。介護士からケアマネになったという経験談ではないため予め断っておきたい。あくまで多くのケアマネージャーと出会ったことからの考察である。
介護福祉士からケアマネへ そのメリットとは
体力的に楽になる
介護の仕事に従事している方からはよく腰が悪いと聞く。職業病だろう。ノーリフトケアとは言っても、やはり体力を使う仕事には違いない。施設勤務では夜勤も行い、神経が休まらないことが多いだろう。
ケアマネになると直接介護するわけではないため、当然、体力的には楽になる。また基本的には夜勤ということはない。
ネットワークの幅が広がる
もちろん職能団体での活動や個人的なネットワークを通じて、自身が勤務する施設外の職員と交流(連携)を図っている方は多くいるだろう。しかし基本的には、施設の中での仕事、利用者宅での仕事が基本だろう。
ケアマネージャーになると、自分が所属する組織以外の方々と連携する場面が格段に増える。ヘルパーやデイサービス事業所など介護関係の事業所だけではなく、病院や行政ともやりとりをすることになるため、自身のネットワークの幅は格段に広がる。
総合的な支援が出来る
もちろん介護をされていて、クライエントのこれまでの人生、背景を知ることもあるだろう。直接支援をしているからこそ身近に感じられ、信頼され、「○○さんだから話すね」というように打ち明け話を聞くこともあるだろう。おそらくそういうことを聞いたら、上長に報告したり、ケアマネに報告するのではないだろうか。
もしケアマネージャーになれば、そういうことを聞いて、では実際にどんな支援ができるか、どんな計画を立てれば望む人生を送っていただけるかと考え、実際に立案することができる。
本人の意向を聞き、周囲や関係機関を巻き込んで支援を組み立てる、これはケアマネージャーだからこそ出来ることかと思う。
介護職に戻るケアマネさん達
さて冒頭に示した通り、筆者が出会ってきたケアマネージャーの中には、ケアマネ業務が合わないと言って早々に介護職に戻る方が居た。そういう方々の思いや悩みとはどんなものだったのか。筆者が聞き及んだ理由をいくつか紹介する。
じっと座って文書を作るのが苦手だった
当然、介護の仕事をしていても支援記録など文章を書く仕事はある。しかしケアマネージャーになればその種類や量はかなり多くなる。しかも内部で使用することのみではなく、外部の機関やサービス事業所に配布する(お見せする)ものも含まれるため、気を遣うことも多い。筆者の友人は書類ごとが心底嫌いで、だからケアマネにはなりたくないと言っている人がいる。
さらにこれまで身体を動かすことが必然の仕事だったため、デスクにずっと座っていることさえ辛いという人も居る。
慣れればどうにかなりそうなものの、文章を書くこと、書類ごとがそもそも苦手であれば、なかなかケアマネの仕事は大変そうだ。
そもそも楽しい面白いと思えない。つまらない。
あるケアマネージャーからは「高齢者の方と会話しながらケアしている方が楽しかった」と聞いた。直接支援をする介護職の方が自分には向いているみたいだと言っていた。
ケアマネージャーが対象者と関わると、話を聞いて、希望に沿った計画を本人家族と考え、それを関係者と共通理解し、支援を行い、評価して・・・という流れがある。介護職の場合と違って、他機関、多職種で連携を図ることが増え、対象者本人以外とのコミュニケーションが増える。
それを楽しいもしくは面白いと思えるか。そう思えなければおそらく、「対象者との直接的な関わりの場面が減った」、「面白くなくなった」ということになってしまう。そういうことで「介護職に戻ります」と言う方がいる。
対外的なやり取りが苦手
「メリット」のところで触れたが、ケアマネージャーとして活動すると、ネットワークの幅が広がる。それは、ヘルパーやデイサービス事業所など介護関係の事業所だけではなく、病院や行政ともやりとりをすることになり、対外的なやり取りが日常的に発生しているからだ。
初めて電話する機関、初めて会う人、何回か会ってるけどなかなか連携が取りにくい相手など、人間関係や連携においてストレスを感じることもある。
こういう対外的なやり取りが苦手となると、ケアマネ業務を行うのはかなりしんどいだろう。これは避けては通れない業務だから。
ご自身に合った職業選択を
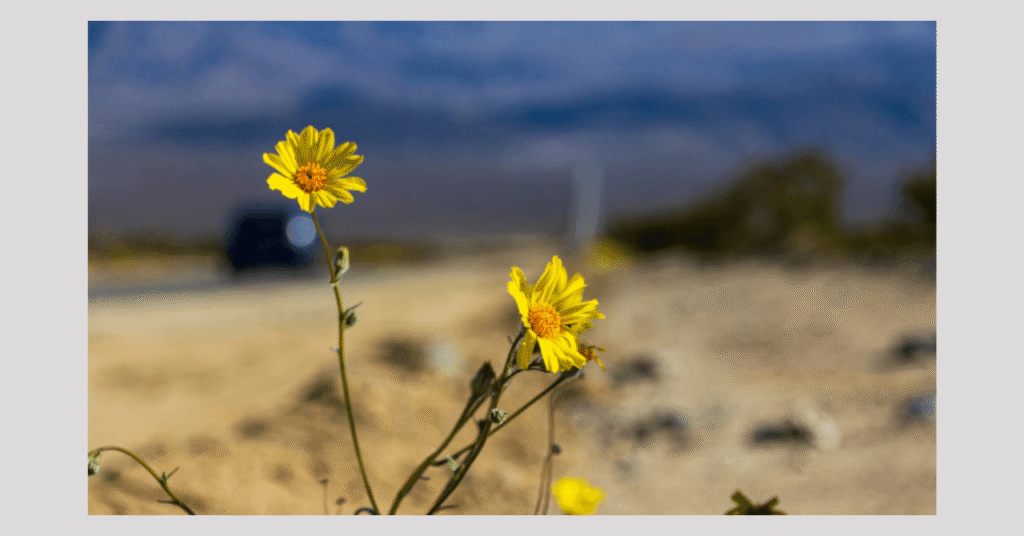
ここまで筆者が出会ってきたケアマネージャーから考察した、介護職からケアマネになることのメリットや「ケアマネ業務に合わなかった」という人たちについて記してきた。
何が得意か、どういうことにやりがいを感じるかは人それぞれであり、あなたがご自身の性格や考え方に沿って納得のいく選択ができれば良いと思う。その選択のために少しでも参考になればと本記事を記したつもりだ。
また、さっそくケアマネになることを決めて、勉強するおつもりの方はこちらもどうぞ。